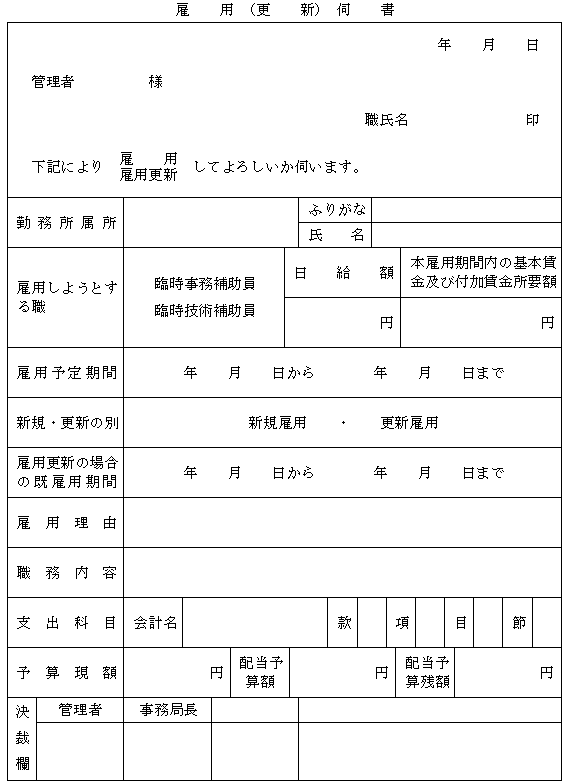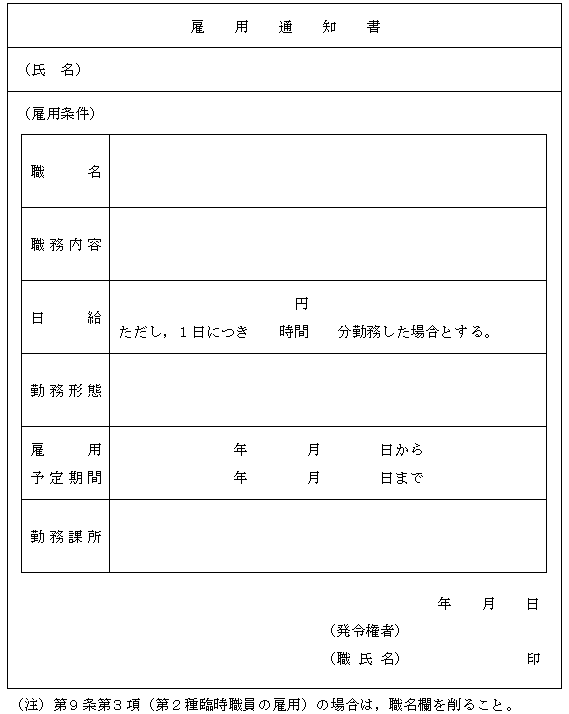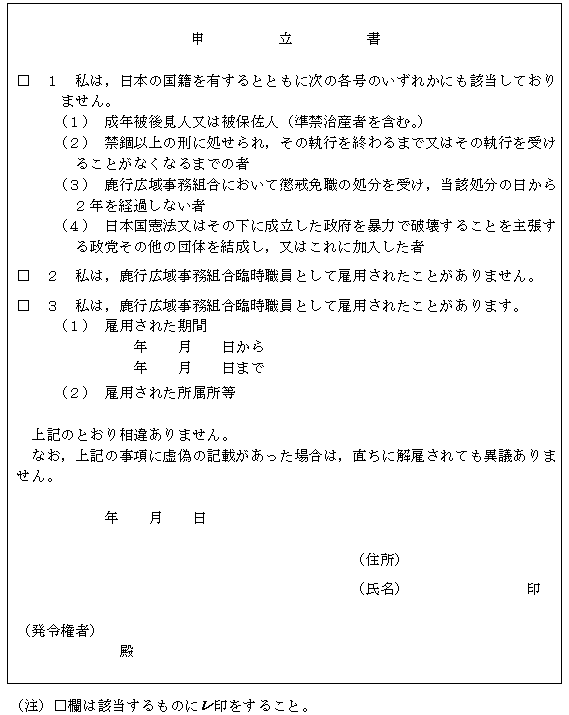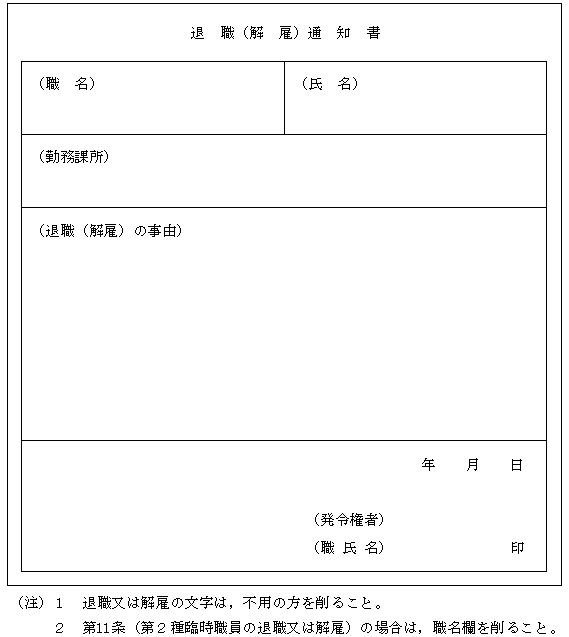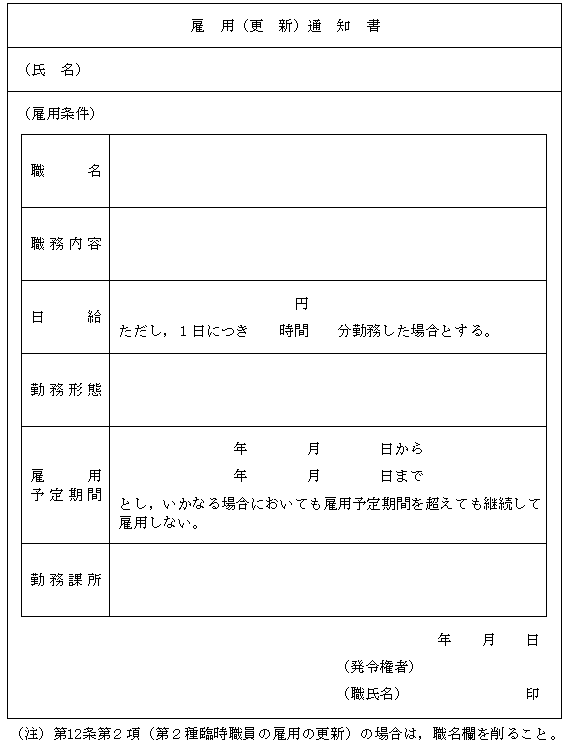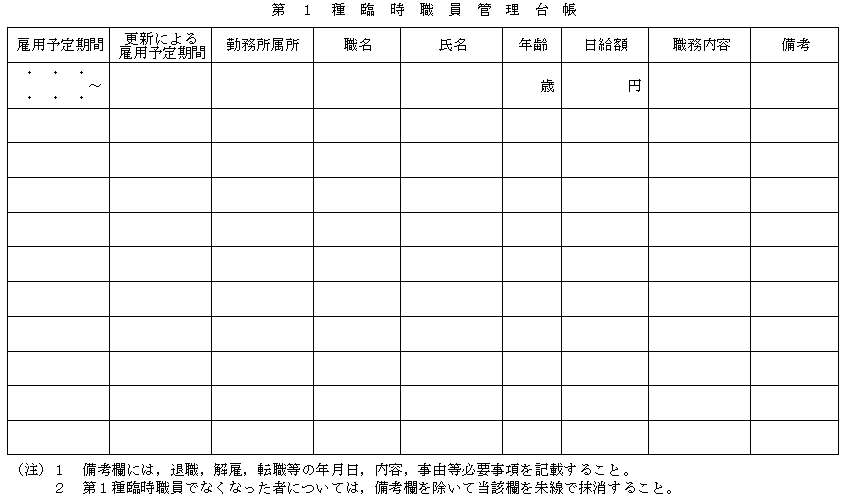|
|
|
| 改正 | 平成8年4月1日訓令第4号 | 平成18年1月12日訓令第1号 |
| 平成23年2月28日訓令第2号 | 平成25年5月7日訓令第4号 |
| 平成25年8月28日訓令第7号 | |
第2条 臨時職員の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
2 前項第1号に掲げる第1種臨時職員とは,職員の療養休暇,休職等に伴う一時的欠員,又は時季的業務に対応するため,雇用開始日の属する会計年度内において1月をこえ6月以内の雇用予定期間を付して日日雇用する賃金支弁の職員をいう。
3 第1項第2号に掲げる第2種臨時職員とは,職員の療養休暇,休職等に伴う一時的欠員,又は時季的業務に対応するため,雇用開始日の属する会計年度内において1月以内の雇用予定期間を付して日日雇用する賃金支弁の職員をいう。
第3条 第1種臨時職員は,その従事する業務に応じて次の各号に区分する。
第4条 第1種臨時職員は,賃金予算の範囲内で雇用するものとする。
3 第1種臨時職員の発令権者は,第1種臨時職員としての被雇用予定者(この条及び次条において「被雇用予定者」という。)に対し雇用通知書(
様式第2号)を交付して雇用するものとする。
第5条 第1種臨時職員の発令権者は,被雇用予定者から次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 自筆の履歴書(履歴書に提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をちょう付すること。)
第6条 第1種臨時職員の発令権者は,第1種臨時職員について,その雇用予定期間の満了前に次の各号の一に掲げる事由が生じたときは,当該職員に退職(解雇)通知書(
様式第4号)を交付して退職させ,又は解雇することができる。
(2) 業務その他の都合により解雇しようとするとき。
2 前項第2号の規定に基づき第1種臨時職員を解雇しようとするときは,解雇しようとする日の少なくとも30日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし,当該職員の責に帰すべき事由により解雇する場合は,この限りでない。
第7条 第1種臨時職員の雇用更新は原則として行わないものとする。ただし,当該職員の従事する事務が雇用予定期間をこえて存続する場合には更新することができる。
2 前項ただし書の規定による更新は発令日の属する会計年度内において6月を限度として行うことができるが再度更新することはできない。
3 第1種臨時職員の更新は,発令権者が雇用(更新)伺書により雇用更新日前10日までに管理者の承認を受けるものとする。
4 第1種臨時職員の発令権者は,第1種臨時職員としての被雇用更新予定者に対し雇用(更新)通知書(
様式第5号)を交付して雇用更新を行うものとする。
第8条 事務局長は,第1種臨時職員管理台帳(
様式第6号)を備えておくものとする。
第9条 第2種臨時職員は,賃金予算の範囲内で雇用するものとする。
2 第2種臨時職員の雇用は,発令権者が雇用(更新)伺書により次条に定める書類の写しを添えて管理者の承認を受けるものとする。
3 第2種臨時職員の発令権者は,第2種臨時職員としての被雇用予定者(この条及び次条において「被雇用予定者」という。)に対し雇用通知書を交付して雇用するものとする。
第10条 第2種臨時職員の発令権者は,被雇用予定者から次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。
第11条 第6条第1項の規定は,第2種臨時職員について,その雇用予定期間の満了前に当該職員を退職させ,又は解雇しようとする場合について準用する。
第12条 第7条第1項及び第2項の規定は,第2種臨時職員の雇用更新について準用する。この場合において,第7条第2項中「発令日の属する会計年度内において6月」とあるのは「発令日の属する会計年度内において1月」と読み替えるものとする。
2 第2種臨時職員の雇用更新は,発令権者が雇用(更新)伺書により管理者の承認を受けるものとする。
3 第2種臨時職員の発令権者は,第2種臨時職員としての被雇用更新予定者に対し雇用(更新)通知書を交付して雇用更新を行うものとする。
第13条 雇用更新を行なって雇用した第1種臨時職員を雇用予定期間に日日雇用した後,更に第2種臨時職員に,又は雇用更新を行なって雇用した第2種臨時職員を雇用予定期間に日日雇用した後,更に第1種臨時職員に雇用換えすることはできない。
第14条 臨時職員の発令権者は,他の発令権者が雇用更新を行なって雇用した臨時職員を雇用予定期間に日日雇用した後,更に継続して雇用してはならない。
第15条 臨時職員の発令権者は,かつて臨時職員として雇用された者を雇用するときは,その退職の日から1月以上経過した後でなければ再び雇用してはならない。
第17条 臨時職員の勤務時間は,1日につき7時間45分以内とする。
第18条 雇用後1月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した第1種臨時職員に対して,翌月から,継続勤務した1月につき1日の年次休暇を与えるものとする。ただし,その者が雇用更新され,最初に雇用された日から6月を超えて継続勤務することとなった場合には,当該超える期間については,この限りでない。
2 第1種臨時職員が雇用更新され,最初に雇用された日から6月を超えて継続勤務することとなった場合には,その者に対して,5日の年次休暇を与えるものとする。
3 前2項の規定による年次休暇は,1日を単位として与えるものとする。ただし,第1種臨時職員の請求により1時間を単位として与えることができる。
4 前項ただし書の規定により1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は,当該第1種臨時職員の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た時間)をもって1日とする。
第18条の2 臨時職員には,
鹿行広域事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年鹿行広域事務組合規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2第2項から第5項まで及び第22項に掲げる有給休暇を,一般職に属する常勤の職員の例により与えるものとする。
2 前項の他,管理者が特に必要と認められた時に必要と認められる期間を有給休暇として与えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか,臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その臨時職員に対し当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 勤務時間規則別表第2の16の項,17の項及び29の項に規定する場合に該当するとき これらの規定に定められた期間
(2) 勤務時間規則別表第2の18の項に規定する場合に該当するとき 必要と認められる期間
(3) 6週間(多産妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の臨時職員が申し出た場合 出産の日まで申し出た期間
(4) 前各号のほか,管理者が特に必要と認められたとき 必要と認められる期間
第19条 発令権者は,臨時職員で社会保険(健康保険,厚生年金保険及び雇用保険)の被保険者の資格を有するものについては,当該保険に加入させるものとする。
第20条 臨時職員の公務上の災害及び通勤による災害については,
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の定めるところにより補償するものとする。
第21条 臨時職員の服務については,
鹿行広域事務組合職員服務規程(平成2年鹿行広域事務組合訓令第2号)の規定を準用する。ただし,臨時的任用上当該規程により難いときは,この限りでない。
第22条 この訓令に定めるもののほか,臨時職員の雇用等に関し必要な事項は別に定める。

様式第1号
(第4条第2項関係) 
様式第2号
(第4条第3項,第9条第3項関係) 
様式第3号
(第5条第2号,第10条第2号関係) 
様式第4号
(第6条第1項,第11条関係) 
様式第5号
(第7条第4項,第12条第3項関係) 
様式第6号
(第8条関係)